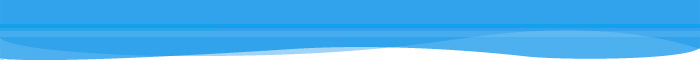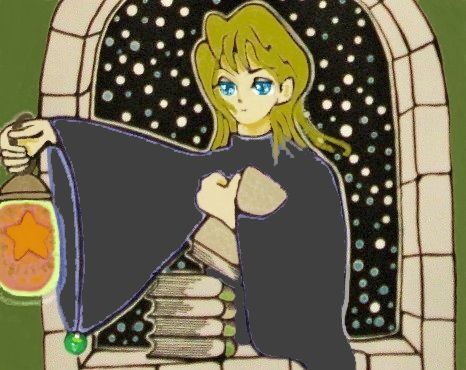「ブルー・マーブル」という
手作り小冊子の詩を推敲して
「こちら、ドワーフ・プラネット」
Yahoo!ブログにUPしたんだっけ。
なぜ同じ名前のブログを継続しなかったか
ふと考えたけど、視点を変えたかったから。
冥王星(ドワーフ・プラネット)
まで引いた視点を
地球(原点)に戻したかったから?
ファンタジーや神話についての夢想は、
日常の七曜(月曜日~日曜日)の外の
はざま時間の埋め草だけども、
大切なひとときってイメージで
冥王星の名をブログにつけた。
それが10年前の自分。
リアルいろいろあって、
夢幻にむしろ
大きな足場を置いている、
夢幻だけど
今を支えるリアルと感じ始めた?
足元の日常で夢想する、それは
エブリディ・マジックの世界観。
fairy と scope も、
それと似た感覚で
選んだ言葉なのかも。
視点を変える……
地球と冥王星。
足元と最果て。
スランプだと感じて
ジタバタしてるけど、
10年も一本調子ムリ。
足元を見直す、むしろ
初心にかえる。
fairy tale(妖精譚)を
探してる……
エブリデイ・マジック – Wikipedia
Wikipedia より「エブリディ・マジック」
低年齢向けの内容のものが多い。日本では藤子不二雄の漫画作品が代表例である。ただし藤子不二雄作品は、系譜としてはファンタジーではなくSF系のショートショートや伝統的な落語からの流れを組んでおり(略)
漫画作品が代表例に。
自分のイメージだと、
エリナー・ファージョンの童話が
「エブリディ・マジック」の感触。
日本では、大正童心主義の作品群。
第二次大戦の終戦後、
戦前の童話は批判された。
開戦時には故人だった宮沢賢治・
戦中に病弱な教師だった新美南吉は、
戦後に作品評価が傷つくことなく、
国語教材等でも有名に。
(不幸中の幸いだったか)
日々の暮らしに不思議をみる感性は、
室町時代の御伽草子~江戸時代の草双紙(絵本)
などにも?
戦後に
「子どものリアルな姿・豊かな自然を描いた」
として評価が衰えなかった児童文学作家は、
宮沢賢治・千葉省三・新美南吉
の三人だったという。
新美南吉は戦時中にも童話を執筆したが、
その作品が戦後の評価にも耐え得たのは、
教師・作家として素晴らしい。
繊細な作風に強靭さを秘めていたと気づく。
もっと新美南吉の作品を読んでみたくなった。
(2020..4.5 Twitter より)
因果交流電燈 – あかり窓 (memoru-merumo.com)